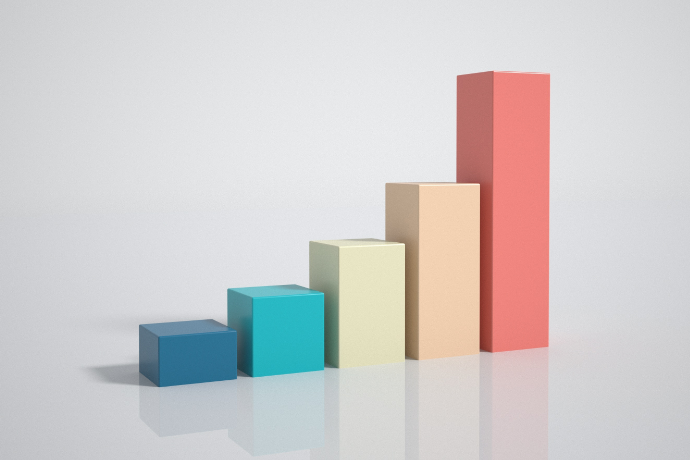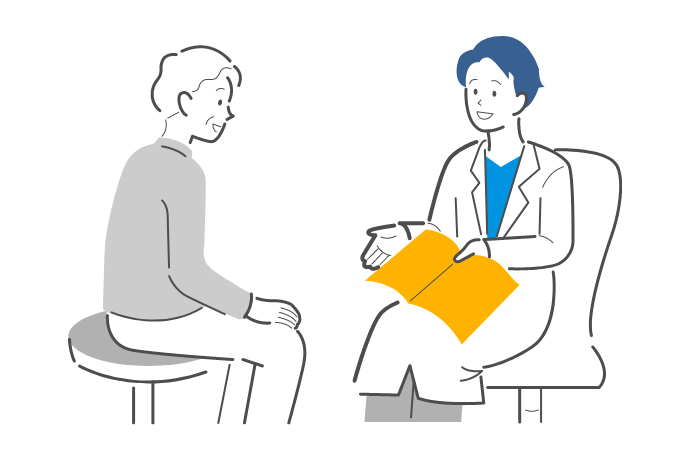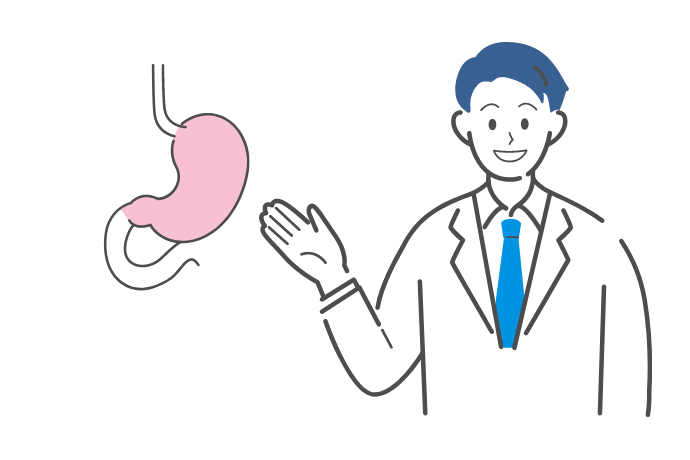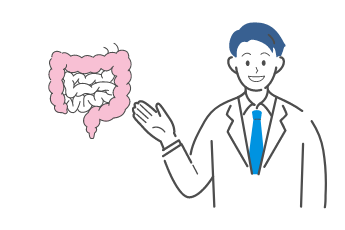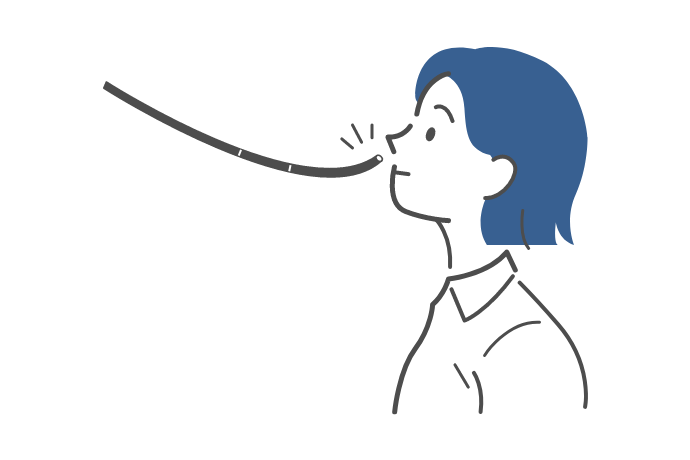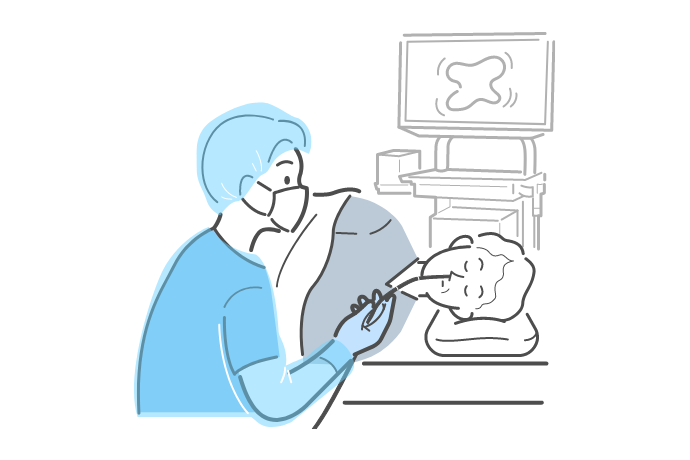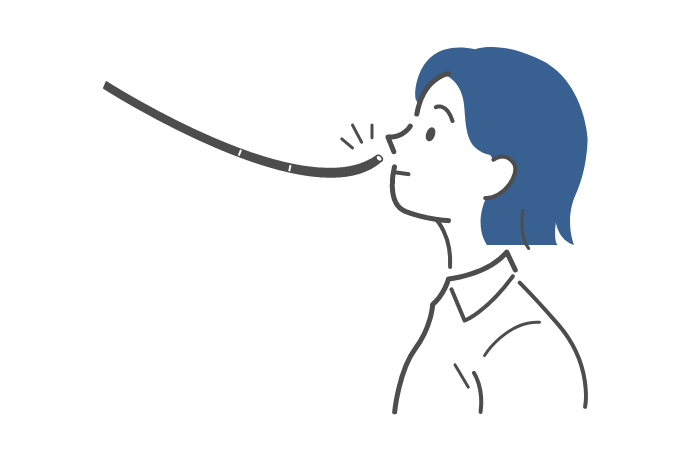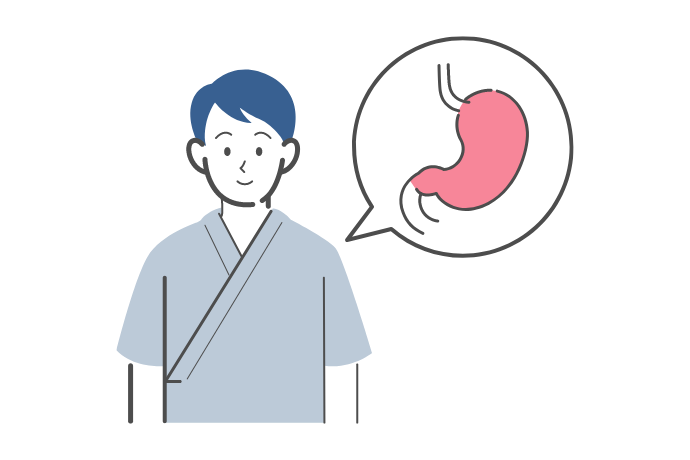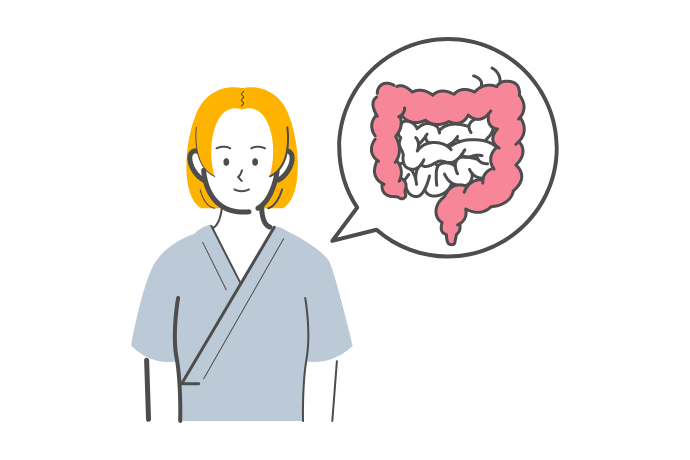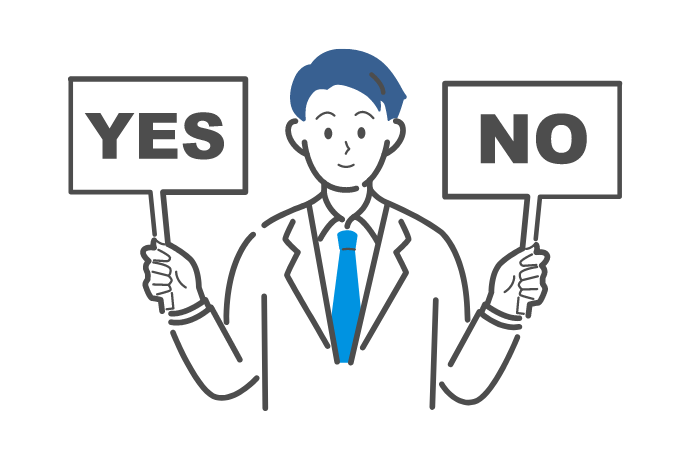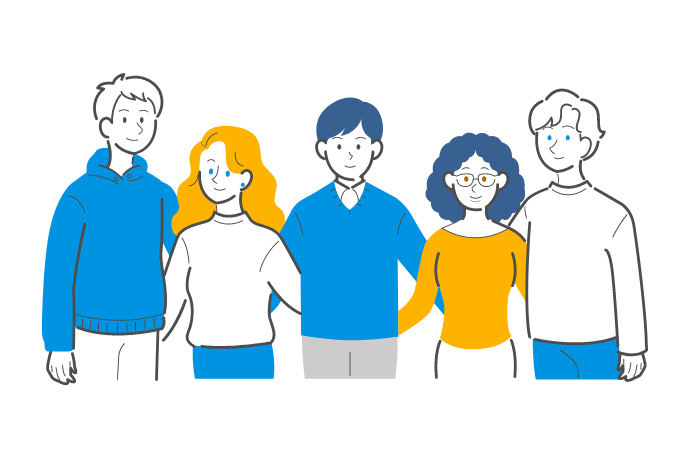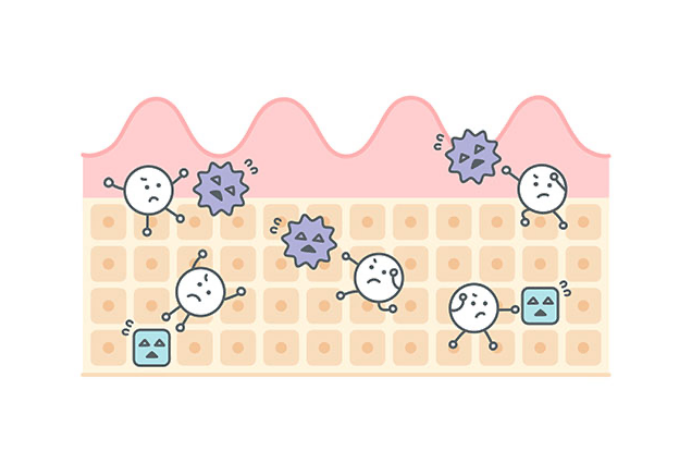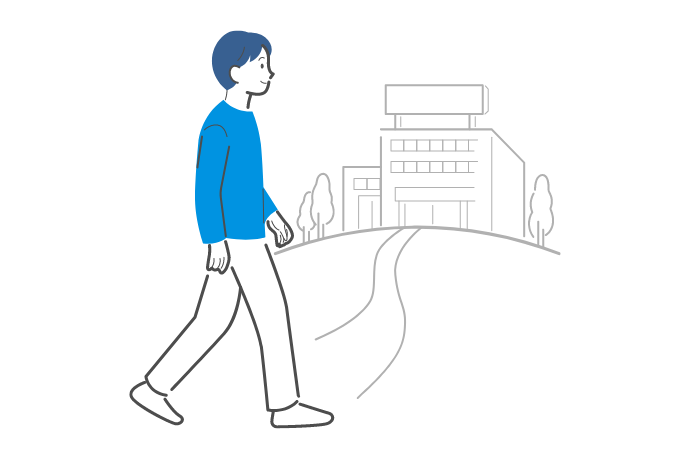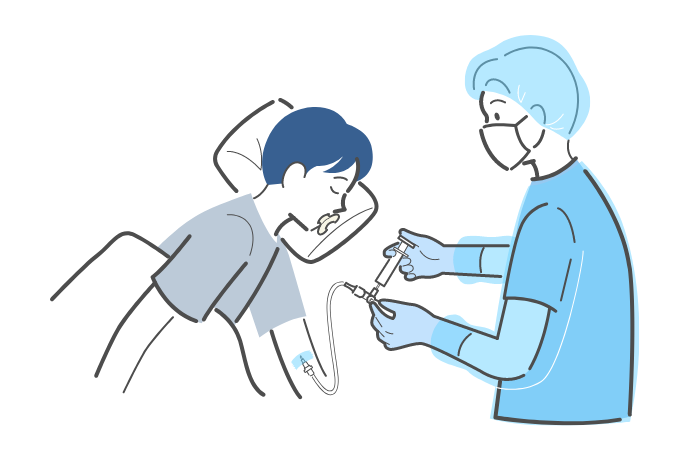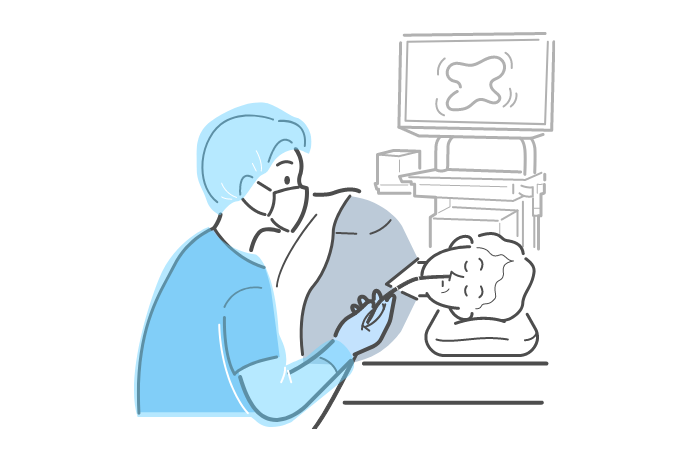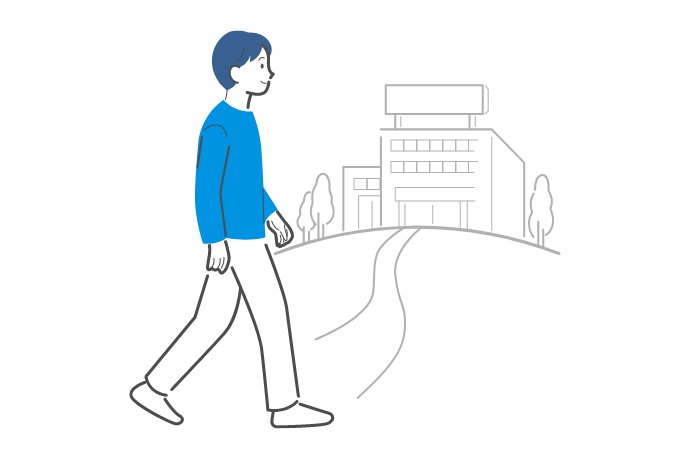がん予防・がん検診を知る
【まとめ】がん検診
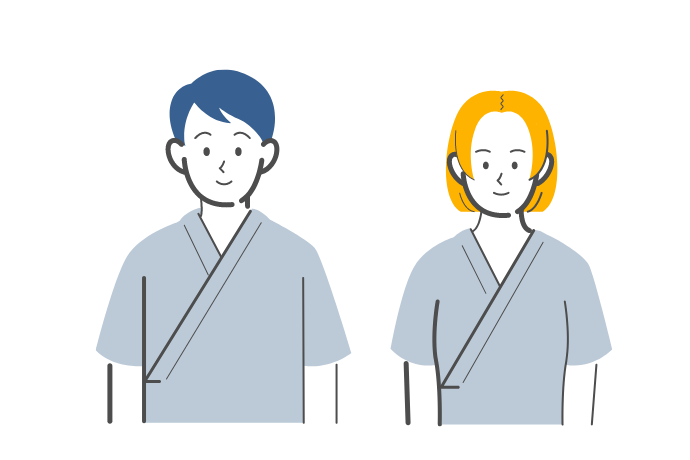
1. がん検診とは
がん検診とは、がんを早期に発見し、発見された場合は早期治療を行うことで大切な命を守ることを目的とするものです。日本では、2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなるといわれています。中でも大腸がん、肺がん、胃がんは罹患数・死亡数ともに多く、がんは1981年以降、死因の第1位です。
一方で、医学の進歩により、早期発見・早期治療ができれば治る※がんも増えています。がんは初期のうちは自覚症状がほとんどなく、発見が遅れがちです。そこで、自覚症状がないうちから定期的にがん検診を受け、早期発見・早期治療につなげることが大切です。
5年生存率に基づきます。
がん検診の目的「早期発見・早期治療」
定期的にがん検診を受けることは、「二次予防」(病気の重症化を予防すること)につながります。日本人の2人に1人ががんになるといわれていますが、早期に治療できれば治るがんも増えています。ステージⅠで治療した場合の5年生存率は、胃がん98.7%、大腸がん98.8%、肺がん91.7%、乳がん100.0%、子宮頸がん93.6%と非常に高くなっています。
がん検診は「症状がなく健康に過ごしている人」が対象で、自覚症状が出る前のがんを早期発見するチャンスなのです。
2. がん検診の対象者と受診期間
厚生労働省は、がん検診の対象年齢・性別・検査内容・受診間隔を提示しています。たとえば、胃がん検診は50代以上が2年に1回、大腸がん検診は40代以上が1年に1回、受診することが推奨されています。これらの対象は主に働き盛りの世代にあたります。
がんはあまりに小さいうちは発見が難しいとされていますが、短期間で進行することがあるため、1〜2年ごとの定期的な検診が重要です。対象年齢が近づいたらスケジュールを立て、早期発見の機会を逃さないようにしましょう。
3. がん検診の種類と検査内容
厚生労働省が推奨する「対策型検診」は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんを対象に、市区町村や職場が提供する検診で受診することができます。検診は1〜2年ごとの受診が効果的で、任意で人間ドックなどを利用する方法もあります。
胃がん検診
胃がんは日本人に多く、男性の11人に1人、女性の24人に1人の割合で診断され、がんの中で罹患数が上位となっています。しかし、早期に見つかれば98%が治る※というデータがあります。ただし、早期では自覚症状が出にくいため、定期的ながん検診の受診が重要です。
5年生存率に基づきます。
大腸がん検診
大腸がんは日本では罹患者数が最も多く、死亡者数も男女で上位を占めていますが、がんの中でも早期発見・早期治療によって治りやすい※がんのひとつです。ただ、初期のうちにはほとんど自覚症状がないため、自分で気づくことは難しいとされています。そこで利用したいのが、大腸がん検診です。
5年生存率に基づきます。
4. 内視鏡検査によるがん検診
胃がん検診には、胃内視鏡検査が選択肢として含まれており、胃部X線検査(バリウム検査)と胃内視鏡検査のいずれかを選択して受けることができます。大腸がん検診では、一次検査として便潜血検査が行われます。便潜血検査で陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査が行われます。職場や医療機関によっては、一次検査として内視鏡検査を選択できる場合もあります。
胃内視鏡検査(胃カメラ)
胃内視鏡検査(胃カメラ※)は、消化管内の様子をリアルタイムに詳しく観察できます。食道・胃・十二指腸の粘膜を細部まで観察でき、わずか数ミリの病変も見つけることが可能です。
「内視鏡」は「胃カメラ」と呼ばれることもありますが、厳密には「胃カメラ」はチューブ状の管の先端に搭載されたフィルムカメラで胃の中を撮影する、歴史上の医療機器のことを指します。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)とは、内視鏡を肛門から挿入して大腸全域の粘膜を詳しく観察する検査です。がん検診(便潜血検査)で要精密検査になった場合や、血便・便通異常などの症状がある場合に行われます。人間ドックや職場での検診で、がん検診として大腸内視鏡検査を選択できる場合もあります。
大腸がんは日本人に最も多いがんですが、早期発見・早期治療ができれば98%が治ります※。この早期発見・早期治療に役立つのが大腸内視鏡検査です。
5年生存率に基づきます。
5. がん検診の費用と受けられる場所
市区町村が実施している対策型がん検診(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん)には、検診費用の補助があり、自己負担額は軽減されています。自治体によって異なりますが、自己負担の料金は平均500〜3,000円程度が多く、無料としている自治体もあります。集団検診は比較的安価で、個別医療機関は割高になる傾向があります。
住民検診は郵送案内や広報誌などで告知され、予約方法は自治体によって異なります。また、企業や健康保険組合が提供する職域検診では、費用の補助がある場合があります。